
- 標準
- 大
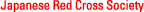
循環器、血液、糖尿病、リウマチ等専門医のいる分野に関しては、医療技術の堅持、いない分野に関しては医師間および他院との連携を強化し、質の高い医療を提供します。
さらに、高齢化に対応するために、地域での医療施設・介護施設との連携を深めます。
また、栄養障害に対する相談等も受け付けております。
血液疾患とは血液に含まれる白血球、赤血球、血小板などの各種成分の異常からおこる病気で様々な病気があります。例えば貧血は、眩暈や息切れなどの自覚症状は一緒でもその原因はいろいろあり、稀に血液を造る場所である骨髄の異常から発生する貧血もあります。
当院では、血液専門医により白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など血液疾患の診療をしております。
なお、骨髄移植は行っておりません。
糖尿病治療の目的は、将来の合併症の発症を防ぐことにあります。そのためには現在のご自身の食事内容の見直しと、運動習慣を身につける事と、糖尿病の正しい知識を身につける事が必要となります。
これらの動機付けとして、糖尿病教室と、糖尿病教育入院を開催しています。
また、認定資格を持った看護師による「看護外来」もありますので、お気軽にご相談下さい。
その他、糖尿病患者さんの会である「さつき会」を発足し、管理栄養士、理学療法士、放射線技師の協力による健康セミナーの開催等、啓蒙活動に励んでいます。
「さつき会」への参加も受付しております。
急性心不全、慢性心不全、冠動脈疾患(狭心症、不安定狭心症、急性心筋梗塞)、末梢動脈疾患(下肢動脈閉塞性硬化症)、肺塞栓、不整脈(ペースメーカー植え込み)、大動脈解離など心臓や血管の病気の治療、管理を行っております。
心臓カテーテル検査室が稼働しており、外来で一般的な評価を行ったのち、心筋負荷シンチ及び心臓CTを行い適応と考えられる患者さんに対しては、経皮的冠動脈形成術(PCI)を施行、もしくは末梢動脈疾患の方には経皮的血管形成術(EVT)、徐脈の方にはペースメーカー植え込み術等行っております。
以下のような症状でお悩みの方はご相談ください。
・胸が痛む、締めつけられる、重苦しい
・背中が痛む
・突然脈が速くなる、遅くなる
・手足がむくむ、しびれる
当院循環器内科では、下記の臨床研究を実施しております。ご理解いただきますようお願いいたします。
超高齢地域急性心不全入院患者レジストリー研究![]()
![]()
RAなどの膠原病を内科的に診察しております。
代表的な疾患の関節リウマチについて簡単にご説明いたします。
人口の1%弱、約75万人の患者数が想定されております。中年に発症しやすいですが若い方や最近では高齢発症の患者さんも多くなってきました。
関節に腫れや痛みが生じ、通常適切な治療が施されなければ関節が破壊されてきます。現在では、早期の診断・治療を行うことで、一般の方達と遜色のない生活を送る患者さんが多くなってきました。
関節リウマチの患者さんには、CRP陰性・抗体検査陰性の方も少なくありません。関節エコーやMRIなどで精密検査を行います。治療には、生物学的製剤も多数使用しております。
当院で対応できない場合には、連携させていただいております「埼玉医科大学病院」へご紹介させていただきます。
関節リウマチはもとより下記のような膠原病を疑う症状で心配な方は遠慮なくご相談ください。
・関節の痛みや腫れ
・こわばり
・筋肉の痛みや脱力
・リンパ節腫脹
・原因不明の発熱の持続
・寒冷時に手指・足趾が蒼白になる
・四肢末端の痛みや腫れ
・ドライアイやドライマウス
・健康診断でリウマトイド因子陽性や抗核抗体陽性、赤沈亢進などの指摘 等
現在常勤医が不在のため、非常勤医師による外来診療を行っております。
気管支喘息、COPDなどの閉塞性肺疾患、呼吸器感染症、肺がんを含む腫瘍性疾患、特発性肺線維症などの間質性肺疾患の診断、治療を行っております。
入院診療につきましては、連携医療機関での対応となる場合がありますのでご了承ください。
神経内科は脳や脊髄、神経、筋肉の病気をみる内科です。
精神科や心療内科と混同されることがありますが、原則として精神=心の病気は扱っておりません。
以下のような症状でお悩みの方は、ご相談ください。
・頭痛が続く
・めまい感がする
・手足に力が入りにくい
・呂律が回らない
・ものが二重に見える
・よく転倒する
・歩きにくい
・手が震える
・感覚が鈍い
・しびれ感がある
・もの忘れ
現在アルツハイマー型認知症は、治療薬があり「早期発見・早期治療」が前提とされております。また、単に認知症といっても原因はさまざまあり、その中には根治可能な認知症もあり、正しい診断・治療がなされれば回復が可能となる場合もあります。
ご自分やご家族で物忘れがひどく困っているなどの症状がある際は、ご相談ください。
物忘れ外来は完全予約制となっております。
ご紹介の際には下記の比企西部認知症連携パスを使用して受診して頂けますようお願いしております。
比企西部認知症連携パス(情報診療提供書)![]()
![]()
もの忘れの状況(チェック表)![]()
![]()
診療担当表(休診のご案内)はこちらから![]()
| 名前(役職など) | 専門医・認定医など |
|---|---|
| 竹ノ谷 正徳(院長(兼)部長) | 日本医師会認定産業医 臨床研修指導医 緩和ケア研修会修了 |
| 三井 隆男(副院長(兼)部長) | 日本内科学会認定内科医 日本内科学会指導医 日本臨床神経生理学会専門医(筋電図部門) |
| 伊東 克郎(部長) | 日本内科学会認定内科医 日本内科学会総合内科専門医 日本血液学会専門医 日本血液学会指導医 臨床腫瘍学会暫定指導医 臨床研修指導医 緩和ケア研修会修了 |
| 住田 崇(部長) | 日本内科学会認定内科医 日本内科学会総合内科専門医 日本内科学会指導医 日本糖尿病学会専門医 日本糖尿病学会指導医 日本静脈経腸栄養学会TNT修了医 日本内分泌学会内分泌代謝科(内科)専門医 臨床研修指導医 |
| 伊藤 達也(部長) | 日本内科学会認定内科医 日本リウマチ学会専門医 日本内科学会指導医 日本血液学会専門医 緩和ケア研修会修了 |
| 吉田 佳弘(部長) | 日本内科学会認定内科医 日本内科学会総合内科専門医 日本内科学会指導医 日本リウマチ学会専門医 日本リウマチ学会指導医 |
| 丸山 崇(副部長) | 日本内科学会認定内科医 日本内科学会総合内科専門医 日本内科学会指導医 日本リウマチ学会専門医 |
| 今井 崇紀(副部長) | 日本内科学会認定内科医 日本内科学会総合内科専門医 |
| 江本 恭平 | |
| 森田 英生 | 日本専門医機構内科専門医 |
| 荻野 太郎 | |
| 竹川 啓介 | |
| 富永 経一郎(嘱託)自治医科大学附属病院より出向 | |
| 平田 まりの(嘱託) | |
| 玄 有希(嘱託) |